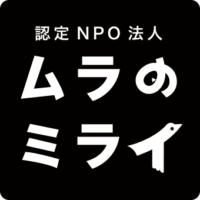原 康子HARA Yasuko
ムラのミライ 事業統括
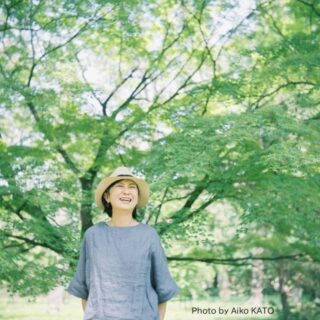
プロフィール
亥年、岐阜県岐阜市出身。
細身のジーンズが苦でなかった時代、修士論文のフィールドワークとして、ムラのミライの活動地(当時)である南インドを訪れたのがムラのミライでの活動の始まり。
インド留学、10年間のインド勤務、5年間のネパール滞在を経て、2016年から京都暮し。 最近の楽しみは、京都のおいしい地下水で淹れるコーヒーと、ベランダ菜園。
1技覚えて、2技忘れるペースで続ける合気道。
提供できる内容(専門分野/講師としての強み)
海外の国際協力NGOや政府機関、また国内NPOや地方自治体を対象にした、住民主体の事業形成・モニター・評価、また各地で住民主体を実現する人材育成のための研修企画と講師要請。特に、子どもも大人も楽になる「子どもとの対話に使うメタファシリテーション」の普及・実践に力を入れている。
実績
住民主体を目指す事業/研修/調査実績
事業:子ども/女性支援
| 2024年~ | 休眠預金活用事業/資金分配団体:ひとり親家庭サポート地域拠点強化事業(埼玉県・岐阜県・京都府・兵庫県) |
|---|---|
| 2024年~ | 独立行政法人福祉医療機構振興助成/団体の強みを活かす子育て支援: NPO組織基盤強化モデル構築事業 |
| 2023年~2024年 | NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ助成業/NPO法人こどもサポートステーション・たねとしずくより委託 ひとり親家庭相談支援者育成事業(大阪府・兵庫県・神奈川県) |
| 2023年~2024年 | 独立行政法人福祉医療機構助成/NPO法人しげまさ子ども食堂-げんき広場-より委託 子ども・子育て支援者対象「子どもの話を聴く技術研修プログラム」(大分県) |
| 2020年~2021年 | 独立行政法人福祉医療機構助成/NPO法人a littleより委託 「半径1.5キロで脱ワンオペ育児:ひとり親家庭への子育て支援」家事サポート基盤整備事業(兵庫県) |
| 2018年~2021年 | ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループ助成 「西宮で広げる、地域で助け合う子育ての輪」プロジェクト *活動の様子はジョンソン・エンド・ジョンソン社会貢献レポート、ムラのミライ2021年7月ニュースレターへ |
| 2004年~2011年 | JICA草の根技術協力事業 南インド・スラムの女性たちによる信用金庫の設立運営支援プロジェクト・マネージャー *活動の様子は原康子『南国港町おばちゃん信金~支援って何?おまけ組共生コミュニティの創り方』(新評論)へ |
分野:地域づくり・地域共生社会
| 2022年~2024年 | 青森県より受託 田子町型地域共生ケアシステム機能向上支援業務(青森県田子町) |
|---|---|
| 2021年~2023年 | NPO法人泉京・垂井より受託/JICA「NGO等提案型プログラム」 「揖斐川流域で学ぶローカル・ガバナンス(地域のお作法)発見方法」(岐阜県) |
| 2020年~2021年 | 厚生労働省受託 予防・健康づくりに関する大規模実証事業に係るコミュニケーションツールの開発・評価等一式(青森県・兵庫県・鳥取県・沖縄県) |
| 2020年~2021年 | 公益財団法人日本国際協力財団受託 NPO法人シェア=国際保健協力市民の会への伴走支援(東ティモールにおける住民参加によるプライマリヘルスケア強化事業 |
| 2019年~現在 | 公益財団法人日本国際協力財団受託 NPO法人エイズ孤児支援NGO/PLASへの伴走支援(ケニアでのシングルマザー生活向上プログラム) |
| 2018年~2020年 | 鳥取県倉吉市社会福祉協議会 コミュニティファシリテータ―養成研修 *活動の様子はムラのミライ2020年8月ニュースレターへ |
分野:国際協力「住民主体のコミュニティ開発」
| 2022年~2024年 | 公益財団法人国際協力財団助成 住民主体型プロジェクト形成・実施のためのメタファシリテーション実践人材の育成(ジンバブエ、ケニア、オンライン) |
|---|---|
| 2021年~2022年 | JICA関西より受託 NGO等提案型事業「NGOによる住民主体型プロジェクト形成・実施のための方法論と技能」(オンライン/東京都) |
| 2022年1月~2月 | JICAイランより受託 「住民参加型地域開発コミュニケーション能力向上ワークショップ」(オンライン) |
| 2016年~2017年 | JICA関西より受託 NGO等提案型事業「コミュニティ・ファシリテーターを育てる実践研修」沖縄県名護市 |
分野:調査
| 2020年 | (株)日本総合研究所 「地域住民参加型の健康づくり施策にかかる調査 」(鳥取県倉吉市) |
|---|---|
| 2018年 | ムラのミライ&a little 「西宮で迎える産前産後の実情調査」(兵庫県西宮市) |
| 2003年~2010年 | 国際協力銀行 インド共同森林管理事業:コミュニティ開発専門家 円借款森林案件(インド共和国タミルナド州、カルナタカ州、ラジャスターン州、アーンドラ・プラデシュ州) |
講演/視察等
| 2024年 | 世界銀行Japan Social Development Fundベトナム事業視察チーム |
|---|---|
| 2024年 | 岩手県立大学総合政策学部 講義 |
| 2023年 | 青森県薬剤師会「多職種連携を進めるためのコミュニケーション技術の活用」 |
| 2023年 | 京都府農林水産部「メタファシリテーション研修ステップ1、2」 |
| 2022年 | 立命館大学「国際協力現場で生まれた方法論を日本で」 |
| 2021年 | 岐阜県関市市民協働課 メタファシリテーション入門講座「身近な人と分かり合う対話術」 |
| 2021年 | 山口県周南市立菊川中学校PTA研修会 「思春期の子どもとのコミュニケーション講座」 |
| 2021年 | JICA中部 「住民を巻き込む多文化共生 国内と海外の事例より〜住民が主体となって地域の課題を解決するには〜」 |
| 2021年 | 立命館大学 現代社会のフィールドワーク「インタビューの実践的学習」 |
| 2021年 | 日本福祉大学アジア福祉社会開発研究センター 「福祉・開発に関わるメタファシリテーション技法の紹介・演習」 |
| 2021年 | 日本福祉大学通信教育部スクーリング 「国際開発と貧困問題:福祉社会開発入門 インドで地域の女性と信用金庫を立ち上げる」 |
| 2021年 | 北陸先端科学技術大学院大学 地域共創スクール第2回参加型ラーニングセミナー「事実質問で関係をつくる技術~メタファシリテーション講座~」 |
| 2019年 | 第10回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会 インタラクティブセッション「考え・感情・事実を聞き分ける〜事実質問の手引き〜」 |
| 2019年 | 2019年度第1回阪神ブロック保健師研究会 「対話型ファシリテーションの基礎~事実質問で相手の本 音を引き出し、対等な関係を結ぶ」 |
| 2019年 | 森のようちえん全国交流フォーラムinぎふ 「「子どものことをもっと知りたいと思ったときの聞き方」 |
| 2019年 | 青森県中泊町/下前&中泊漁業協同組合 青森県あぐりヘルスアップ事業「第一産業(漁業)に従事する方たちへの健康・予防のアプローチを対話を通じて行うための研修」 |
| 2018年 | 弘前大学医学部附属病院腫瘍センター 「医療者のためのコミュニケーションンスキルトレーニング (基礎編)」 |
| 2017年 | 東京女子大学 創立100周年記念連続シンポジウム「グローバル社会に生きる女性のエンパワーメント:女性を支える金融—途上国におけるマイクロクレジットの成果と課題—」 |
| 2017年1月 | JICAカンボジア事務所 NGO-JICAジャパンデスク「NGO 等活動支援事業」によるメタファシリテーション基礎講座講師 |
| 2016年 | 名古屋大学 グローバルリーダー論「現場のリアリティに届く話し方」 |
| 2016年 | 福山市立大学 市民公開講座「南の国の支援されるおばちゃんたちの本音と建前、見分け方」 |
| 2016年 | 関西大学 非常勤講師(後期)「International Development(英語)」 |
| 2016年 | ムラのミライ 「猪鹿庁×ムラのミライで農村集落の獣害最前線を解体」研修講師 |
| 2014年~2016年 | JICA NGOアドバイザー派遣(特定非営利活動法人 難民を助ける会AAR Japan、特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン、特定非営利活動法人ハンガー・フリー・ワールド、特定非営利活動法人チャイルド・ファンド・ジャパン) |
| 2005年~2006年 | JICA 技術協力事業「インドネシアにおける市民社会の参加によるコミュニティー開発(PKPM)」短期専門家(コミュニティ開発)派遣 *西田基行(2018)『PKPM:ODAの新しい方法論はこれだ』文芸社 |
メディア出演
| 2022年 | 京都三条ラジオカフェ「国際協力のノウハウを子ども・若者支援に」 |
|---|---|
| 2021年 | 岐阜新聞「問題解決へ対話の鉄則」関市 |
| 2018年 | 京都新聞「言葉一つ一つに着目 信頼気づく〜海外で培った対話法で子育て支援〜」 |
| 2015年 | FMレキオ 「ハップステップジャンプ」出演 |
| 2015年 | 岐阜新聞「ネパ—ル地震体験記〜岐阜のおばちゃんが被災」(1〜5回)寄稿 |
| 2015年 | ふぇみん婦人民主新聞 「おばちゃん発 “支援しない技術”」 |
| 2015年 | NHKラジオ深夜便 「列島インタビュー」出演 |
| 2014年 | 朝日新聞「著者に会いたい “支援しない技術、岐阜弁で”」 |
著作
- 原康子(2018)「多職種連携,意思決定支援に役立てるメタファシリテーションの実践(連載)」『地域連携 入退院と在宅支援』日総研出版
- 原康子(2014)『南国港町おばちゃん信金〜 ‘支援‘って何?「おまけ組」共生コミュニティの創り方〜』新評論
言語(上から順に得意なものから)
- 日本語:岐阜弁(会話も可)関西弁(聞き取りのみ)
- 英語:国連英検A級。南アジアの人にかなり通じるインド訛りの英語。インド人が読む英語ニュースでは、聞き取りレベルが一気に上がる。
- テルグ語:テルグ語の映画(例:バーフバリなど)を字幕なしで見ることを困難だが、簡単な会話が字幕なしで聞けたときが嬉しいレベル。
- ネパール語:わずかな語彙力を駆使して、道案内ができ、お店で立ち話ができるレベル。